ALL
2022年7月

求職者の6割が見落とされている?
政府の水際対策が6月より大幅緩和されたことを受け、 観光地では人手不足が叫ばれるようになりました。 総務省の労働力調査によると、 求人数は徐々に回復傾向にあり、 本格的に人材獲得時代に突入しそうです。 一方で、転職者数はコロナ禍で 大きく減少しました。 この事実だけ見ると、 中途採用はかなり厳しい状況にあるようですが もう1つ面白いデータがあります。 それは転職希望者が増加傾向にあるということです。 これは転職を望む人は増えているけど、 実際に転職をした人は減っているということです。 原因はいくつかあると思いますが、 ひとつは企業側が求職者に適切に情報を届けられず、 魅力づけできていないことが考えられます。 前提として、求職者は大きく2つに分けられます。 ・転職顕在層 ・転職潜在層 転職顕在層とは、転職先を積極的に探している人たちのことを指します。 この層は転職サイトに登録し、自ら企業に応募をしたり、 選考を受けることがほとんどです。 一方の転職潜在層は、転職の意欲はあるものの、 実際には転職活動を行っていない人たちのことを指します。 そして、この転職潜在層の割合は、 求職者全体の約6割を占めると言われています。 多くの企業は転職顕在層に向けての活動がほとんどですが、 今後は転職潜在層に向けた活動が重要になっていきます。 どのような行動が重要かは次の機会に解説させていただきます。
synergy-admin
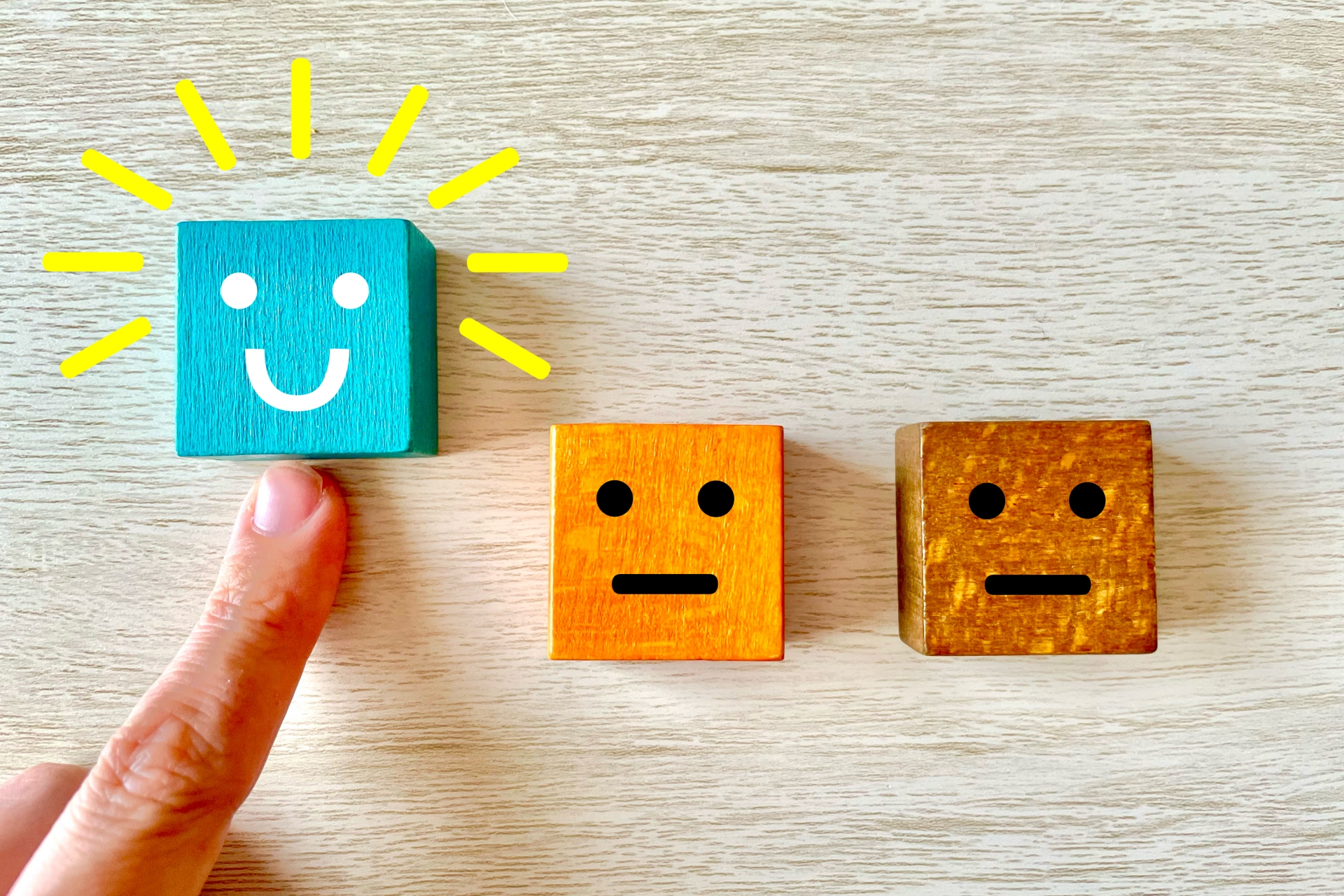
クランボルツに学ぶキャリア理論と経営者の役割
先日、高校の教師の先生方と 「私たち教師や経営者は若者をどう育てるか」というテーマで 討論しました。 抽象的なテーマではありますが、 様々な意見が出て非常にワクワクしました。 ちなみに”若者”は法律的に年齢が決まっているわけではないので このときは15歳~25歳くらいまでの人を対象にしました。 色々と議論を重ねた結果、 「若者と一括りにすることはできない。 我々教師や経営者が育つ環境をどう整えるかが重要」 という結論に至りました。 若者といっても、育ってきた環境や家庭環境が違うため 個性がそれぞれ違います。 どんな個性を持っていても、その人が育つ環境を 作ることが私たち大人が作ることなのだと思います。 1999年に発表されたクランボルツによるキャリア理論によると、 ビジネスパーソンとして成功した人のキャリアを調査したところ、 そのターニングポイントの8割が本人の予想しない 偶然の出来事によるものだったそうです。 つまり、キャリアを構築していく上で、 そのターニングポイントの殆どが予想することが 難しいということです。 よくあるキャリアプランの立て方は、将来の目標を決めて計画を立て、 それに向かって積み重ねていくというイメージだと思います。 しかし、変化の激しい時代において、 将来の社会や会社の状況は個人の意思でコントロール不可能です。 故に効果的なキャリアプランは立てにくくなっています。 クランボルツが提唱する理論はあえて明確なゴールを定めず、 現在に焦点をおいてキャリアを考えることを推奨しています。 理論の骨組みとしては3つあります。 予期せぬ出来事がキャリアを左右する 偶然の出来事が起きたとき、行動や努力で新たなキャリアにつながる 何か起きるのを待つのではなく、意図的に行動することでチャンスが増える つまり予期せぬ出来事が起きたときに行動できるだけの準備をしたり、 偶然の出来事に遭遇すべくフレキシブルに行動したりすることで チャンスが生まれるということです。 目標に固執せずに現在を見るには勇気が必要ですが、 とても大事だと思います。 予期せぬ出来事がいつ起こるかわからないため、 それがいつ起こっても良いように 個人は準備をしなければなりません。 予期せぬ出来事が起きた時に成功しやすい行動特性は、 以下の5つです。 好奇心:新しいことに興味を持ち続ける 持続性:失敗しても諦めずに努力する 楽観性:何事もポジティブに考える 柔軟性:こだわりすぎず柔軟な姿勢をとる 冒険心:結果がわからなくても挑戦する 起きた出来事や周囲の変化を意識し、受け止める姿勢がキャリアの成功には大切です。 これは、新しい出来事や成功体験ばかりではなく、失敗体験にも当てはまります。 出来事を前向きに捉えることが今後のチャンスへとつながるでしょう。 出会いに関しても同様のことが言えます。 たまたま連絡した友人、街で出会った人、SNSでつながった人など、 誰から良い知らせがもたらされるかはわかりません。 偶然の出会いこそ大切にした方が良いでしょう。 また偶然の出来事や出会いを必然へと変えるために最も大切なことは、 あらゆる出来事に関心を持つことです。 偶然の出来事は、起きた時点ではどのような結果をもたらすのかわかりません。 未来が予想できないほど変化の激しい時代において、 用心しすぎるよりも、挑戦してみることが重要です。 キャリアの8割が偶然の出来事によると考えると、 成功しやすい5つの行動特性を身につけられる環境を整え 今をどう生きるかを我々大人がしっかりを伝えていくことが、 これからの若者が育つきっかけになるのではないでしょうか。

小濱亮介

インナーブランディングと企業価値の高め方
経営者は、企業価値をブランディングによって高めようと考えることがあります。 確かにブランディングは重要ですが、対外的なブランディングを意識するあまり、 社員がブランディングを意識しておらず、外面だけが良いという会社もあります。 社員が企業価値を認めていない会社は、いずれ世間から評価されなくなるでしょう。 今回はインナーブランディング(社員に対してのブランディング)の 重要性や効果、必要なことについて紹介します。 インナーブランディングが持つ3つの重要性 ①社員の働きがいに影響する インナーブランディングは、社員の働きがいに影響します。 自社に誇りを持っている社員と、自社に諦めを感じている社員は、 どちらがしっかりと働いてくれるでしょうか? インナーブランディングの成否によって、 社員のモチベーションに大きく影響を及ぼしますので、 対外的な広告と同じくらい、社内的なブランディングも重要なのです。 ②社外への噂が広まる 経営者の中には「社長は孤独なものだから、社員から嫌われても構わない」と 考えている人がいらっしゃいますが、この考え方は少々危険です。 経営者を嫌っている社員は、会社自体に不満を持っていることが多いため、 自社に対してマイナスイメージがあります。 そして、社員には家族や友人がいて、SNSのアカウントも持っています。 社員による噂が対外的に広がる可能性があります。 ③採用活動に直結する インナーブランディングができていると、採用活動にもその影響が直結します。 悪いクチコミの多い企業は、受験者数も少なくなりますし、 その分、採用活動費もかさんでしまいます。 逆に、良いクチコミが多い企業や、社員が活き活きと働いている企業であれば、 受験者にもその雰囲気が伝わるでしょう。 良い人材は良い雰囲気の企業に集まるため、インナーブランディングは重要なのです。 インナーブランディングの3つの効果 ①商品サービスが向上する インナーブランディングができていると、商品サービスが向上する傾向があります。 たとえばリッツカールトンのような一流ホテルを想像していただくと、 そのホスピタリティーの高さが伝わってくるかと思います。 リッツカールトンは、「クレド」という理念やミッションを持っており、 社員が共有しています。 誇り高い企業で働く社員は、自分自身も誇り高く働き、 結果的に商品サービスが向上するのです。 ②顧客満足度が上がる 商品サービス力が上がると、自ずと顧客満足度が上がります。 また、自社ブランドにそぐう顧客が集まってくるため、 顧客の質も上がりやすくなります。 クレーマーのような顧客や、無理難題を押し付けてくる顧客を、 ブランド力によって撃退することができるでしょう。 ③離職率が下がる インナーブランディングの良いところは、離職率が下がるというところにも表れます。 離職率が高い企業は、常に求人募集をしており受験者からも問題があると思われやすくなり、 採用活動の経費が割高となります。 離職率が低ければ、余計な経費を払う必要がなくなるため、 日ごろの企業活動に専念することができるでしょう。 インナーブランディングに必要な2つのこと ①自社ブランドの分析 インナーブランディングをしようにも、そもそも自社の企業価値を理解していなければ、 インナーブランディングのしようがありません。 まずは自社がどのような企業であり、どこを目指すのか、 どんな顧客と取引したいのかを分析してみましょう。 いいかえれば、「理念」「ビジョン」「マーケティング」の3つの要素を 最初に検証する必要があります。 自社の姿が分かれば、戦略が立てやすくなるため、必ず取り組むべき内容です。 ②システムによる業務効率化 インナーブランディングで重要なことは、社員が快適に働くことです。 業務に無駄が多ければ、社員の不満が高まり業務上のストレスとなる可能性があります。 そのようなことがないように、業務システムを導入して、 サクサク働ける環境を提供しましょう。 インナーブランディングは、会社の足元を固めるためにとても重要です。 社員から支持されていない企業は、足元から崩れてしまいます。 企業価値と社員が考える価値は類似するものとして、 手を緩めずに取り組む必要があるでしょう。 プレジデントアカデミー7月のテーマは「ブランディング」です。 小さくてもファンに囲まれる会社になるための方法をご説明します。 気になる方はこちらから詳細をご確認ください。

樋野 竜乃介
