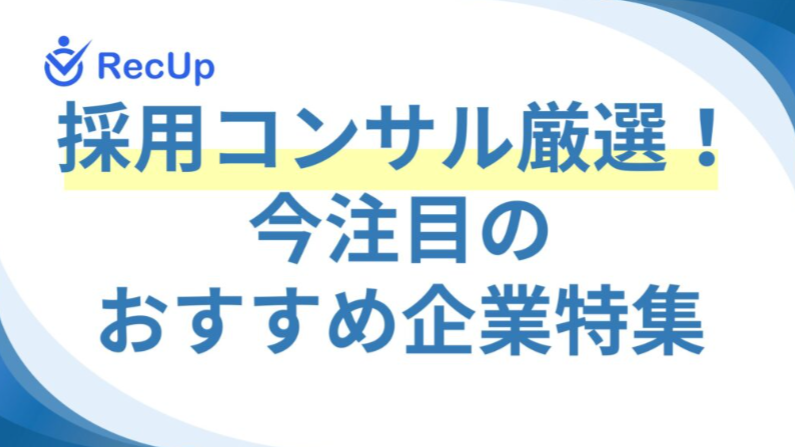ALL
広報シナジーの記事
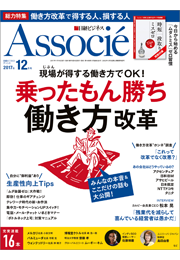
日経BP社の取材
日経BP社が発行する 日経ビジネスAssocie という雑誌があります。 そこでは 日経BP社とレバレジーズ㈱が タイアップした企画で キャリアアドバイザーが勧める 働きがいのある注目企業 100選 という特集が組まれます。 大変ありがたいことに 私たち株式会社シナジーも この日経ビジネスAssocieの企画に 取り上げて頂きました。 こんな地方にまで取材に来て頂く なんてとてもありがたいことですが 最近こういった取材に来て頂く 機会が増えたように感じます。 大変ありがたいことです。 どの様に原稿が作られるの 今から楽しみです。 こうした取材であらためて考えさ せられることは 「自社の強みはなんですか?」 と、聞かれて簡潔に 伝えることの難しさです。 自分たちの強みは 一言で「何」なのかということ。 当然、会社は一つの要素で 支えられているわけではないので 努力しているポイントは 多くあるはずです。 しかし、それを まんべんなく余すことなく 説明してしまうと 他社にない「独自の強み」を簡潔に 説明することができなくなります。 わかり易さというのは とても大切な要素です。 どんなに良い会社でも その良さが分かりにくかったら 採用することはできません。 A社 会社の良さ 100 × わかり易さ 50% 採用力 50 B社 会社の良さ 70 × わかり易さ 100% 採用力 70 入社するのはB社になります。 自分が求職者の立場に立ったとき わかり易さは大事な決定要因に なっているはずです。 しかし 発信者側に身を置いてしまうと 多くの担当者はそれを忘れて しまいがちです。 わかり易さを 採用力の一部と 考えれているかどうか。 会社の良さをわかり易く 伝える努力をしているかどうか。 多くの中小企業は ・風通しがよく ・アットホーム ・若い時期から挑戦できる ・社長との距離が近い など、 テッパンのフレーズが あります。 確かに良いところですが 他の企業がどのように 表現しているでしょうか。 本当にそこが強みだとしても 他社に埋もれてしまう表現なら それは無いのも同然です。 徹底的に考えて 意味のある「強み」を表現 していく必要があります。 本当に、しっかりと考え抜いて 伝えていかなければなりませんね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

【悲報】日本では、「やる気のある社員はたった6%」だそうです
世論調査や人材コンサルティングを 手掛けるアメリカのギャラップ社が 世界各国の企業を対象に実施した 従業員のエンゲージメント調査 (仕事への熱意度)を昨年5月に 行ったのはご存知でしょうか。 日本は「熱意あふれる社員」の 割合が6%しかないことが 発表されて話題となりました。 米国の32%と比べて大幅に低く 調査した139カ国中 132位と最下位クラスでした。 企業内に諸問題を生む 「周囲に不満をまき散らしている 無気力な社員」の割合は24% 「やる気のない社員」は 70%に達しています。 今までは「会社人間」と言われた 日本の会社員は会社への帰属意識を 徐々に無くしてきています。 何が熱意を奪っているのか それでも仕事への熱意が なぜここまで低下したのでしょう。 これは私の個人的な感覚ですが 日本人に「やる気があるか」と尋ねて 本音で「やる気満々」と答えるのは 初々しい新入社員くらいで 多くの人は 「やる気がないわけではないけど、 熱意があるかと聞かれると そこまでは言い切れない」 という感じです。 また、他国の結果と合わせてみると 韓国、中国、香港、台湾といった 東アジアの近隣国は日本の状況と ほとんど変わりません。 ここから見るとこの数字には 国民性や地域柄という要素が 含まれていると考えられます。 すぐに、アイ・ラブ・ユーと 口にしてしまうアメリカ人と 熱意が溢れてますとは言わない 奥ゆかしい日本人との国民差 はしっかりと理解しなければ なりません。 他にも調査対象の雇用環境や 賃金の状況などは各国でばらつきが あるでしょうから この調査結果をもって 日本のビジネスマンが 「熱意がない」「やる気がない」 と決めつけてしまうのは 少し状況を見誤ってしまう 可能性があると思います。 しかし、国民性の違いがあるとは 言っても米国では32%の人が 「熱意がある」と答えています。 やはり日本の低さは際立ちますし これは確実に日々の仕事ぶりや 生産性に跳ね返ってくるでしょうね。 求められるマネジメントの変化 日本は1960~80年代に非常に よい経営をしていたと言われます。 他の国も日本を模倣していました。 問題は近年の若者が 求めていることが管理を されていくことではなく 自分の成長に重きを おいていることです。 それ以上に問題なのは 『不満をまき散らす無気力な社員』 の割合が24%と高いこと。 やはりマネジメントの手法を 変えていかなければ ならなくなったといえます。 一昔前は、上司の言ったことを 口答えせずに確実にやれば成功する というのが従来のやり方でした。 しかし現在は 上司と部下が一緒になって どう結果を出すか 部下をどうやって成長させていくかを 考えることが上司の仕事になりました。 これまでは弱みを改善することに 集中するのが上司の仕事でしたが 得意でないことが強みに 変わることはあまりありません。 この好きで得意なことに 集中することで米国では 『熱意あふれる社員』 の割合が高まり生産性も 上がったと言われています。 つまり大切になるのは 部下の強みが何かを上司が 理解することだといえます。 少なくとも、日本よりも 熱意のある社員の割合が 高いのは事実だといえる でしょう。 好きで得意なことに 集中してもらうことで 熱意ある社員を増やすことが できれば業績向上につながることは 間違いありませんが そのためにはマネジメントの あり方を変える以上に 経営者のマインドを変えなければ いけません。 嫌なことでも我慢し ストレスを貯めながら 生活のために働くものだと 考えてしまうと 社員一人ひとりに目を向ける ことができません。 中小企業は経営資源が少ないもの。 高い給料で釣って、頑張ってもらう という手法を取りにくいことを 考慮すれば 好きで得意なことに しっかりと集中してもらうのが 一番生産性を上げることに 繋がるわけです。 でも、経営者のマインドが 仕事は嫌なことを我慢して 行ったことに対する対価 と考えている以上は この溝は埋まらないものに なるでしょうね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

闘将の采配力
楽天の星野仙一球団副会長が 4日に亡くなったと発表がありました 70歳で、死因は明らかに なっていないそうです 現役時代は中日のエースとして活躍し 引退後は中日、阪神、楽天の監督を 歴任されました 何より、計4度のリーグ優勝を飾り 楽天時代の13年には 初の日本一に輝きました 17年に野球殿堂入り 「燃える男」 「闘将」 と呼ばれ、巨人を倒すために野球人生を ささげてきた男がこの世を去りました 沢村賞を受賞した74年には V10を阻止して優勝しましたが 「日本シリーズは邪魔 俺は巨人を倒したからいいんだ」 と言い切ったほど 巨人を倒すことに執念を燃やしました 「強い巨人に勝ちたいんや」と その思いは引退後も変わることはなく 常に打倒巨人を掲げていました 印象的だったのは 2003年の 阪神のリーグ優勝 2013年の 楽天のリーグ優勝&日本一 2003年の阪神のリーグ優勝は 就任1年目で 18年ぶりの優勝という快挙 当時は金本、伊良部を獲得し コーチには田淵を招集 今岡誠、赤星憲広 藤本敦士、吉野誠ら若手が 急成長し首位を独走して 7月8日には セ・リーグ史上最速となる 優勝マジック49を点灯させます 圧倒的な強さでリーグ優勝 2013年の 楽天のリーグ優勝&日本一は 2012年の布石がよく 星野チルドレンと呼ばれる 釜田佳直、辛島航 枡田慎太郎、銀次などの 生え抜きの若手を抜擢し 活躍させましたしリリーフだった 美馬学を先発に転向させるなど 人材活用のうまさを随所にみせました しかし、何よりもすごかったのは 2013年、3人の現役メジャーリーガー アンドリュー・ジョーンズ ケーシー・マギー 斎藤隆を獲得したこと ドラフトでは2位で則本昂大を指名し 2013年の開幕投手まで任せます 大切な開幕戦をプロ公式戦経験が ない新人選手に任せるのは実に 29年ぶりのできごとでした その後則本、田中将大と 過去に見ないほどの偉大な記録を 打ち立てて弱小楽天は 優勝しました 星野監督が好きだった 弱小チームを強くして優勝に導く そういったのは監督業の醍醐味でしょう 当時弱小だった 阪神タイガースや 楽天イーグルスというチームを 優勝させたからすごいのであって やはり巨人を優勝させたとしても 星野監督がこれほどまでに 「名将」と騒がれることはありません しかし、巨人を倒す その思いだけでは 決して弱いチームは強くなりません 星野監督は確かに 「士気」を上げるのも上手でした しかし、何よりも オフシーズンの戦力補強に 真剣でした 企業経営も同じですが 戦力補強 士気向上 戦略立案 この3つは監督と同様 中小企業の社長にも求められます そのどれがかけても 上手くは行かないでしょう どんな人材補強をして やる気になるしかけをつくり ビジネスモデルをいかにつくるか ビジネスモデルが悪く 人材の能力が低いのに よいサービスができ よい結果が得られるかというと もちろん無理がでます チームをどう作るかという大切さを 星野監督の功績は 教えてくれたように思います 勝つチームを作るには 人材確保が優先事項 この有効求人倍率で 採用活動をするのは 簡単ではありませんが 人材の重要性を教えてくれる 偉大な事例です ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

東広島を襲った11月の”3.11”
東日本大震災から今年で 7年を迎えます 東日本大震災で多くの 犠牲者を出した仙台市では 津波のおそろしさを 忘れないようにと なんと元旦から 避難訓練が行われ 住民が津波避難タワーに 避難するという活動がされ ているようです まだ、3.11の爪痕が 東北には残っているんですかね 同じく東日本大震災による 津波で大きな被害が出た 福島県浪江町の請戸地区では 避難指示が解除されて ”初めて”迎える元日となり 町民らが海岸沿いで 初日の出を眺めたといいます 避難指示の解除からやっと 7年目でようやく 自宅に戻れたんですね 本当に長い時間 大きな影響を受けています 11月の3.11 同じく東広島においても 3.11が襲ってきていました 今日、広島労働局の 雇用関係統計を見ていると ハローワーク 広島西条の有効求人倍率 が、なんと 3.11 この 有効求人倍率というのは 求職者数に対する 求人数の割合で 雇用動向を示す 重要指標のひとつです 景気とほぼ一致して動くので 景気動向指数の 一致指数となっています 1.0を上回れば 採用競争が生まれ 1.0を下回れば 就職競争が生まれる そんな簡単でもないのですが シンプルにいうとそんな指標です 全国平均の 有効求人倍率が 1.56 あの愛知県の 有効求人倍率が 1.86 オリンピック特需の 東京都でも 2.12 3.11が どれ程に採用が難しいかが わかってもらえるかと思います ちなみにコレは約2ヶ月前の 実績になりますので現在とは 違うわけですが つい先日まで有効求人倍率は 1月 1.90 2月 1.95 3月 2.03 4月 1.94 5月 1.94 6月 1.95 7月 2.07 8月 2.29 9月 2.58 10月 2.76 もともと全国平均、愛知県の 平均よりも高いのですが 夏以降の加速度は目を疑います あらためて、ここを知った上で どのようなチーム編成をして 行く必要があるのかを考え なければ求人費をムダにします ひとつの解決策として 現場で活躍する人たちの 事務作業をいかに減らすか 実は 事務業務については 全国平均でみても 広島西条でみても 0.45~0.55付近で パートでも フルタイムでも 採用しやすくなっています 値上げ調整を行い 利益効率を上げ また採用し易い事務職を強化し バックオフィス業務をしっかり 支えることで 現場負担を軽減していくことが 数字的にみると必要だと 言えるかもしれませんね 他の仕事に比べやりがいの うすい職種はこれからは 組織づくりすらままならない そんな時代になってきています 本当、3以上は未知数ですね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

1万社で1500人を取り合う
新卒採用を取り巻く環境は かなり厳しく かなり難しい状況です 18卒の平均求人倍率は 1.78倍 6年連続上昇を続けており 19卒はさらに上昇するでしょう 1.78倍という数字だけみれば そこまで高いとは思えず 健全な数字に見えるかもしれません しかし、これはあくまでも 全社平均です 企業の従業員規模別で 見てみると5000人以上の企業の 平均は0.39倍 ※低い! 反対に300人未満の企業は 6.45倍となっています もう少しかみ砕いて説明すると 300人未満の企業の採用目標数の 合計が1万人だとするとそこに 応募してくれる学生は 1500人しかいないということです 逆に5000人以上の企業の 採用目標数の合計1万人だとすると そこに2万5000人の学生の応募が 殺到するということになります 中小企業においても優秀な学生を 採用したいと考えますが マーケットはこんな状態なので 取り合いになるのは避けられません こうした中で、採用を成功させるには ブレない覚悟と体制が必要です 毎回伝えていますが 中小企業は社長を含め 全社で採用に関与していかないと 採用はまったく上手くいかない 時代になりました では、何に気を付けて どういった採用活動を していけばいいかというと ポイントは 1.母集団を増やす 2.選考途中の離脱を減らす 3.内定辞退を減らす いろいろあるように感じますが この3つがポイントです その中でも普段あまり伝えませんが 選考途中の離脱を減らすことを考えます まず取り組めることは 選考期間の短縮化です 説明会参加から一次選考 一次選考から二次選考といった 次の選考への期間を最大でも 5営業日として 早め早めに内定を 出していくのも良いでしょう その代わり 面接や選考回数を多めにして しっかりと何回も会いつつ お互いを知る工程を設ける そして、意外と取り組んでいない こととしてあるのが 面接官のスキルアップです 採用は営業活動と同じです 自社の商品の魅力を 正しく理解してもらい 購入してもらうが 「自社の魅力を正しく理解してもらい 入社してもらう」となるだけです 営業に求められるのは 正しいヒアリングをし そのお客さまに合った 営業活動をすることで お客さまから信頼されること 採用に置き換えると採用担当者が 学生から信頼を得られているかが 大きなポイントになります そのためには短時間で 学生からの信頼を得る必要がある 面接担当者のスキルアップが急務 となります 私の経験からすると 役員クラスの面接担当者こそ スキルアップが必要だと感じます 中には学生の話もよく聞かず 自分の話ばかりしてしまう人もいます 我々が信頼できない会社から ものを買ったりしないのと同じで 学生も信頼できない会社に 入社しようとは思いません 学生から信頼を得ることが 内定承諾に結びついていきますし 入社後のパフォーマンスにも 影響してきます 面接担当者の 面接練習をぜひ しっかりとやってみましょう ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

入社3ヶ月の壁
さて、2018年という 響きにもなれてきましたね 今年のカープはどうなるんでしょう 去年は3年目右腕が 薮田が大ブレイクでした 交流戦で中継ぎから先発に転向し そこからリーグ2位の15勝を挙げました 初のタイトルとなる最高勝率(.833)に 輝くなど、黒田博樹が引退した投手陣 の救世主となりました 3年目の離職 この3年目って 結構難しいんですよね 企業の場合、よく3年目の離職率が 話題にあがります 実は厚生労働省が発表する 資料によると1年目、2年目、 3年目と離職率に差はありません つまり、3年目に目が向きがち ですが1年目、2年目のどの 段階においても、離職率には 大きな差はないわけです 1年目の離職を防ぐポイントは 入社3ヶ月にあります なぜ入社3ヶ月なのか? という点ですが、会社に入って 一生懸命に頑張って ふっと気が抜けたり 迷いが生まれるタイミングが 一般的に3ヶ月頃になります 色々学んで、良い点も悪い点も 気づきを得る余裕が 入社して3ヶ月経つと生まれます そこで3ヶ月の壁に焦点をあてて 考えてみます 3ヶ月目の壁 さて、「壁」とは何でしょう? 新入社員は、3ヶ月目に 何を考え出すかというと ・上司や先輩って言うことと やることが違うんじゃないの? ・誰も助けてくれない ・誰も構ってくれない ・もっと他に理想の職場って あるんじゃないのかな? というようなものが多いようです 教育・コンサルティングを専門に 行っている企業が新卒者向けの アンケートを行い分析すると 2017卒は プラスの傾向値になったもの ・自己実現の意識がやや高まっている ・真面目で、素直、学習意欲が高い ・周囲を見て、協調して行動する その他の傾向 「合格点主義」で全力を出さない という思考からもう少し悪く 「テストに合格できなくても 許されるならそれでよい」 という傾向に変わっています 自己都合の合格点主義という 意識があるといえます つまり、がんばりきれないのに 「こんなもんだな」 (自分なりにがんばったからOK) と、自分で線を引いてしまう傾向 があるようです ※株式会社ジェニック 2017年春入社員意識調査結果分析より 計画的な社員教育を こういった意識を生ませないために 新入社員教育は欠かせないものに なってきます では、新入社員教育はどのように 行うのがよいかというと 会社全体で考えなければなりません 考え方として 現場は 時間が空いているときに教育 → 時間をとって教育 採用責任者は 現場に配属するまでが責任 → 現場で成果をだせるようになるのが責任 入社3ヶ月までの教育プログラムを 事前に作り、目的、効果、担当を 設定しておくのが有効です 面談のタイミングも 事前に決めておくことで 「何かあったら聞いて」 といって本人からの申し出に 依存しなくても良い状況を 設計しておいてください 今年も採用シーズン本番が 迫っているのに新卒社員が 入社して採用チームは 本当に大変でしょう^^; 活動は計画的にしてくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

稼げる新人
元旦から知人と採用に 関する話をしていました 採用の相談されるだけで とても嬉しいものです^^; そのときに出た言葉は 「採用だけならできるけど 結局はその後が大事だよね」 そう。 ほんっとに、そうなんですよねぇ 中小企業でも固有の魅力を しっかりと高めていけば 良さそうな人を採用するのは できるようになります でも… でも、結局はその人が活躍できる かどうかが大切なわけです 現場の社員に任せてしまうと 「人材」ではなく「人手」を欲しがる 採用を進めてしまいます 確かに、現場の人手不足感は 多くの中小企業の課題になって いるんですけどね^^; だけど 人手採用も 人材採用も 結局は同じ「人」なんです 実際に人手として採用した 人材に期待せずやってもらうと その”人手社員”の温度に 巻き込まれてポテンシャルの 高い人材の温度も徐々に 下げてしまいます 人手が欲しいのであれば 新卒ではなくても良いでしょうし 新卒採用にはしっかりと 将来を期待できる「人材」を 採用するように決めてください そして、その採用した人材の 教育をどのようにするのか やっぱりここは大切です 間違いなく新卒の新人は 即戦力にはなりません 成果が出せるようになるまで じっくりと育てる必要があります たしかに、新卒は会社に フレッシュな風を吹き込んで くれるんですけれどすぐに成果を 出せというのは酷です ノウハウや経験もないので当然です 当社もそうでしたが 新卒入社した新人の多くは 1〜3年の間は「お客様扱い」 となってしまいます しかし、仮に 「新人が2年間、成果を出せない」 という場合、大きな問題があります なぜなら、入社2年目の社員が 1人前になれず、成果を出せないと 翌年の新卒社員が入ってきたとき 成果を出せない社員が2倍に 増えてしまうからです 新卒を仮に5人採用すると 翌年には10人の成果を出せない 社員を抱えることになります 3年間お客様扱いしていれば 15人前後の成果が出せない 社員が生まれることになります こうした状況はダイレクトに 生産性低下につながります こうなると大きなハンディキャップ になってしまいますので 入社時の教育が必要になります できれば、この教育を 社内でやるのが理想です 基本的には毎月1日12回は 自社の社員&社長でしっかりと 教育を行うのがオススメです 1ヶ月に1回宿題を出してその宿題を しっかりとやりきってもらうなど 運営側の負担を減らしつつ新入社員を 手塩にかけることが大切です 手間暇をかけていないのに 中小企業の将来を支えてくれる 人材が育つわけがありません 最初のうちは外部研修に出すのも 良いかもしれませんが しっかりと手間暇をかけた 社員教育を行っていくことが 大切です その後はどうやっても その専門性やノウハウは 局所的には専門社員の方が 高くなるわけですから 話が脱線しましたけど 新入社員は1年で稼げる人材に なってもらうことが必要です 1年で稼げるようになるために 毎月1回は1日研修として 時間をとってしっかりと新人教育を 行うようにしてくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

不惑
毎年、もう恒例となっている 龍王山初登頂に行ってきました 毎年元旦の日の出を大勢で見る 一年のお祈りするのが 自分にとってのお正月の恒例行事です 「シナジーにたくさんの笑顔が溢れますように」 「スタッフみんなが充実した一年が送れますように」 「シナジーが存続し、発展しますように」 手を合わせ心からお祈りです 今年の初日の出は曇っていて 完全な光がわかりやすく差し込む っていう感じではなかったんですが 自分の気持をセットするには 十分なものでした やはり、初日の出っていいものですね 押し付けがましく言うわけでは ありませんが気持をリセットする よい習慣だと思います^^; この一年は、部下の小濱が マネージャーとして 随分支えてくれました この一年でもっと成長してくれる と思いますし、実際にいいチーム になっています 小濱を支える後藤真紀子が 今年で5年目に入るので どういう成長をしてくれるのかも 本当に楽しみです 社長の次男坊も 随分と頑張っていますが 今年が正念場 クレドミーティングのときでも まさに「忍耐力です」って言われて 踏ん張ってくれているのがよく わかります 彼はいい時期に来てくれました 警備事業部のメンバーも 各々の強みを持ち寄って 盛り上げてくれています 支えらればかりではなく しっかりと支えていかないと 自分の最大の誇りは 今のメンバーたちで そのシナジーの一員でいる ということに他なりません もっともっと強くて 愛溢れるシナジーになれるように しっかりとリーダーの自覚を 持ち続けようと思っています 今年のキャッチフレーズですが 「re」(アールイー)に決めました 2010年にシナジーの キャッチフレーズで使いましたが あらためて このフレーズを登場させます 「re」とは「再び」という意味で 接頭語として使われています 「reset」「restart」「retry」 「restructure」(再構築) 「rebirth」(生まれ変わる) 積み上げてきた大切な 価値観はしっかりと守ります 例えば 「おもてなしの心」 例えば 「パートナーさんを大切にする気持ち、行動」 例えば 「クライアントの結果にこだわる姿勢」 でも逆に必要のないものまで 大切に溜め込んできていることもあります そこはしっかりとresetし 今まで目標として掲げたものの 達成できなかったことにretryし 新たにrestartする 一年にしたいと思っています 今、39歳 今年は40歳に突入します 不惑の40代 この40代というのは 自分の命・自分の力 自分という存在を もっと、多くの人のために 世の中のために この世界のために 自分という存在と その力を使っていきたいと 考える年齢のようです^^; この1年で自分の思いが どのように動いていくか 自分自身でも興味がありますが 自分という存在が この世界に果たせる役割を もっと明確にして挑戦して いきたいと思います みなさん、どうぞ また一年間よろしくお願いします! 2018年元旦 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

大晦日日記
なんでこう年末って せわしいんですかね いつもと変わらない月末の 一つのはずなのですが。 年を跨ぐというだけで 気持ちは全然違いますね あらためて1年を振り返ると いろんな変化があった1年 好ましい変化もあれば 好ましくない変化もありました^^; こういった変化を読むのではなく 自分自身で変化をちゃんと創り出す そういった人になりたいものですね また来年を どう考えていくのか 向き合う日々です 今年も多くの人とお会いしましたが 事業がうまく行っている社長さんで 苦労を経験していない人は いませんでした あたりまえですが 失敗や苦労を乗り越えた経験を 糧に前進しているひとばかりです そんな中小企業の推進をしっかりと 支えることができる1年にしたいものです ためてる仕事 たくさんあるな・・ 年明けガッツリ 取り組みますので 今日は1年お世話になった 方々から連絡があったり こんな取り組みをしているよ って、教えてもらったり あらためて1年を振り返る 時間にもなりました 忙しい中連絡をくださった 皆様ありがとうございます こうやって人との つながりを感じています 人で癒やされて 人で傷ついて やっぱり軸になるのは いつも人です さて、新しい年まであと数時間 今年もこうして一年を振り返える 時間を過ごせることに 今はただ感謝しています いつも誰かに支えて 来てきてもらいました 支えてもらうばかりでは 申し訳ないので来年は もっとしっかり支える側に 回りたいと思っています 今年もたくさん 「ありがとうございます」を 言わせていただきました 今年最後の 「ありがとうございます」 を送ります みなさん、一年間 ありがとうございました〜!! ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

ベンチマーク人材の有無
社員は転職活動は面倒なので 誰も進んでやりたいとは思いません 避けられるものなら 上司のつまらない発言や 人事の厳しい方針も目をつぶり できるだけ今の職場で 続けようと努力するものです 最終的に今の会社に 自分の才能をささげる 価値がなければ 優秀な人材は退職します 転職の相談を受けている人の 話を聞くと 経営者が社員の思いに 応えていない そういった部分に課題を 感じているのか と、実感します 確かに、経営者が みんなの意見を聞いて 方向性を決めていれば 社長の存在なんて いらないわけです みんなで話をして みんなで答えを出せばよいので ただ、世間はそれでうまくいく わけでもないので 経営者が考えないといけないものも 多々あるのも事実です だからこそ 社員の意見を聞き続ければ よいかというとそんなことありません しかし、この社員の意見は 無視するとおかしなことになる というメンバーの意見は ちゃんと聞くようにする必要があります なんとかなるだろう と思って、押し切ったところ 実際にはどうにもならなくて ボロボロになる なんていうケースもあります しかし、一旦押し切って ボロボロにならなければ そういった目に見えない 境界線の判断はできません 後は、本当の本当に ボロボロになって判断するか 予兆で調整できるか こういったところは 経営者の勘所に左右されます なぜならば、具体的な被害が まだ出ていない状況で 切り替えるのは難しいものです すき家の 「牛すき鍋」でオペレーションが 崩壊しましたが 経営者は 崩壊してはじめてダメだったと わかるわけです ただし、現場も責任がありますので 簡単に崩壊させられていては やってられません だからこそ、この人の意見は しっかりと聞かなければならない というような、ベンチマーク人材 の存在が重要になってきます 今回相談を受けている人は 条件や待遇は抜群によく 条件で考えれば 辞める必要が無い環境です それでも 思いや方向性が違う ということもあり、転職を考える 本当にもったいないことですが みなさんの会社も ”彼の意見だけは、聞こう” 的な存在はいますか? しっかりと基準になる存在を 作ってくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

10年
10年一昔といいますが 平成19年3月にシナジーに入社して 今年で丸10年を迎えました 前回は7年で転職したので ベテランというほどでは ありませんでした ベテランというとやはり 20年、30年のような人を いうんでしょうか 10年はまだまだです^^; 一口に10年と言っても それでも、途方もなく長いのが10年 過ぎてしまえば あっという間だった思える10年も 考えてみれば一日一日の積み重ね その一日一日も 本当に色々なことがありました 年末に一人で振り返っていると ふとそんなことを考えます そんなに優雅な時間を 過ごしているとはいえ ないんですけれどね^^; 大変なことがあると その度になんのために これをするのか ということを考えました 事業の中心が常に「人」に 強く依存するビジネスを しているので この1年は採用が 簡単にできないこともあって 随分ともがいている感じもします そんな中で 未来に向けてつくる 事業計画と向き合う なかなか苦しい作業です 事業計画書は 事業のことを 深く理解して 深く考えないと書けません 書くのが苦しいということは 事業を熟知しきれていないか 普段から深く考えていないか 自分の事業のことを よく理解できていないと こういうことになります よくわからないから 逃げてしまいたくなる 自分の事業を しっかりと理解せず 安定的な運営をするのは とても難しいもの 中小企業の90%程度は 事業計画をつくっていないと いいますが つくっていないのではなくて つくることができないのが正解 なんでしょうかね つくることにワクワクする 年もあれば つくることがとてもしんどい 年もあります 入社して10年 いろんな計画を考えてきましたが 散らかっていた方向性は 徐々に集約されている感じが 心地よくもあり 申し訳なくもあります そのときは良かれと思い 始めたサービスも 時代の流れや 会社の変化にともなって やるべきではないものも でてきました 自分にとって 年末年始は そういったものを 少しずつ見返していく 大切な期間なので しっかり向き合いたいと 思います 今年もあと2日 それにしても 年末年始の休みは短いですね^^; 考えがちゃんとまとまるかな 年明けにはもう少し スッキリとしておきたいものです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

理想と覚悟
家族を理由にして辞める という話をされて 「家族の人生まで背負えない 後はお前が決めることだ」 と、伝えたと ある社長さんから聞きました 本当に悲しそうな 顔をしていました もし、そんな日が来たら 家族までを背負ってでも 前に進んでいこう そんな覚悟ができる メンバーで仕事をしていこう そう心に誓った日を 思い出しました 中小企業は不完全だから 迷うし、泥まみれで かっこ悪いかもしれない でも、それくらいで あきらめない そんなしぶとさが 何よりも必要になります 会社が成長するに従って サービスの質が落ちたり 仕事をする楽しさが劣化しては 会社を大きくする価値がない 仕事を楽しめる会社でなければ いけないし 小さかったときにはできない サービスを提供して お客さんにも喜んで欲しい 色々な葛藤を抱えながら 来年度の計画に向き合う瞬間 時間を重ねることで 少しずつ本質に 近づいている実感 理想への覚悟を 問われている時間です ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

クレドよりも採用
よし、これでいこう! という ミッションを固め 未来のビジョンを明確に描き 評価制度も連動させる 社内の発信も欠かさないようにする そう頑張っていくことで 組織は少しずつ変化していきます しかし、組織の中にはいくら頑張っても 変わらない人がいます それは、そもそも社長やリーダーや 組織の価値観に共感していない 人たちです 正直にいって どんな人でも共感する というビジョンなどこの世の中には 存在しません 人の感情というのは、千差万別 ある人にとってはとても魅力的でも まったくそう感じない人だっているでしょう あたりまえのことですが そのあたりまえのことに 立ち向かっていくのも 小さな会社の社長の仕事です なぜなら、みらいへのビジョンと こだわりを整理した結果 それに共感できないという社員が 必ず組織の中から出てくるからです それは、ミッションを軸にして 人を採用してこなかった 結果だといえます 知り合いの紹介ということで 採用したり 近所だからという理由で 採用したり 条件がちょうどよかったという理由で 採用する 短期的にはいいかもしれませんが 長期的に考えると このような採用は必ず会社として 求心力を弱める結果になります 結婚式の相談に行って そこのスタッフが冷めた目で対応 していたらどう感じるか いくら提案が良くても 専門性が高いとしても 社員の思いは顧客に伝染する ところからスタートします クレドを作っている会社は 随分と増えました 言語化され、明確化された 行動指針やルールが 大切なのはいうまでもありません しかし、クレドに沿って行動すれば 誰しもが会社が求める人材になるか というと決してそんなことはありません クレドを何よりも重んじる会社は クレドを守るために採用にもっとも 力を注いでいます それは そもそも資質をもった人材しか 会社の求める人材になり得ない ということを意味しています 価値観を共有する組織が作りたいと 本気で考えるのであれば 最初から価値観が 一致する人材を採用すること 価値観の共有はできても 価値観の強制は不可能だからです だからこそ採用は大切です その大切な採用の成功率を ぐっとあげる 会社の価値観に共感した人材を 採用できるイベントを行います 中小企業向け選抜 新卒採用スカウト型イベント Gメン32~中小企業のための新型・新卒採用イベント~ 開催日時 2018年02月25日(日) 10:30~18:00(10:00~受付開始) キャリアカウンセリングを受けて 事前に中小企業に入ってもいいという 意思をもって優秀な人材だけを選抜した 採用イベント です https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/52308/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

好きで得意なこと
文部科学省は26日、教員の 「働き方改革」を進めるための 急対策を正式に公表しました 教員が有給休暇を 取得できるようにするため 夏休みなどに学校閉庁日を 一定期間設けるよう促すことや 文科省内の複数の課に またがっている 教職員に関する業務を 一元的に管理する部署を 新設することなどが 盛り込まれました 「働き方改革」は 第2次安倍内閣が 発信した政治課題です 雇用・労働政策の中でいえば これほど大きな政治課題となった テーマは過去に見ません そうなったのには 明確な理由があります それはこれまでに積み上がった 多様な社会課題が 「働き方改革」 という一つのテーマに統合された からだといえます この働き方改革の流れは 大きく5つの要素が合わさって 発生していると考えています 1.更なる賃上げ アベノミクスで 企業業績は回復し 賃上げもなされたが 低迷した消費が改善されない 2.長時間労働の是正 欧米諸国と比べ労働時間が長く 20年間改善がみられない 3.第4次産業革命 金融サービス事業のフィンテック 等をはじめとするAIのロボット による省力化 4.人手不足 労働生産人口の長期的な減少と 好景気を背景とした求人難 5.一億総活躍 少子化対策を起点とした 女性が活躍できる経営推進 これら5つの要素をすべて 「働き方改革」 に解決が託されているといえます しかしその流れを 止めようとするのが 私たちの慣れている 日本型の雇用システムです 例えば、長時間労働の是正は 従来の雇用システムそのものを 変えなければ 「働き方改革」と叫んでも 何も変わりません 現場を預かるマネージャーの戸惑い 働き方改革に関する 生産性向上の好循環を回そうと したときにボトルネックになるのは 現場のマネジメントだといえます 現場を預かるマネージャーは 業績責任を負っているため 突然、理想論ともいえる 残業削減を命じられても 簡単には納得がいきません 「業績を犠牲にして 早く帰ることに戸惑っている」 というのが正しいかもしれません 悲しいことに 様々なデータを見ると 労働時間と業績には相関関係は なさそうです 取り急ぎ、古いですが リクルートワークスさんから拝借 マネージャーは短期的な 生産性を求めますが 経営者は継続的に生産性を 高めることを求めるので 経営者とマネージャーでは 狙っているものにずれが出ます 働き方改革では マネージャーの現場調整が 最大の課題だといえます 生産性を最大まで上げようと思うと 不得意なことをするのではなく 好きで得意なことをしっかりと やってもらう ということになるのですが どうにも、それが許せない 人が世の中には多いようです 好きで得意なことを 追求できる会社が一番 成果が出やすい そのような個性化が 今後のあたりまえになっていくと 思います 実は、専門性が高くなること以外にも 個性化が進む要因があります それは、歳をとるということ 若いときは同僚よりも出世したい という基準で頑張っていた人が 年齢を重ねると 「自分にとって何が大切なことか」 というものが基準になります それによってその人らしさが 決まってくるため 個性化が加速します 好きでもなく 得意でもないことを 我慢してやっている会社よりも 好きで、得意なことを 追求している会社のほうが やはり生産性が高くなるはず 多様な強みを伸ばして プロの集団になる 好きで得意なことこそが 働き方改革の根幹になると 考えています みなさん、好きで得意なこと していますか〜? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

8割は「気合」と「勘」
韓国の百貨店や 大手スーパーを運営する 「新世界(シンセゲ)グループ」が 来年1月からイーマートなどの全系列社の 労働時間を短縮し、週35時間勤務体制に シフトすると発表しました 韓国大手企業では 初となる大幅な労働時間の短縮です 実は日本に限らず韓国も 長時間労働 過労死が常態化しつつある 労働文化を持っています アジアにおいても少しずつ ワークライフバランスに人々が 着目していることが伺えます 韓国の世論は 大手の「英断」を評価しつつ 懐疑的な意見も多くみえます 「そもそも、今週40時間勤務が 守られていないのに達成できるのか」 「9時出勤17時退勤て 法的に普通なのでは……?」 すでに「机上の空論」と 言われんばかりの声が多数上がっています 人手不足は日本国内に限らず 世界的な潮流のようです ライフワークバランスを向上させ 企業の魅力を高めようと 努力をしますが 世間は机上の空論と 冷ややかな目で 見られることも多いようです 机上の空論の大切さ 計画をつくると 「机上の空論」と 揶揄されることがあります 確かに、現場で実践している 人からしてみれば勘や嗅覚が 鈍ると成果がでなくなります そういった現場で実践している 人たちからしてみても 本当の意味での「直感」で 場当たり的に判断して 行動しているかというと そんなことはありません 成果を出している人は 必ずと言っていいほど 何かしらの型を持ち それを勘の源泉として 大切にしています 理屈は基本的には後付なので 研ぎ澄まされた嗅覚の方が 優れていると言わざるを得ません 理屈では説明がつかない 勘のようや嗅覚が 勝負の8割を決める 実際にはその通りだと思います 8割が理屈では 説明がつかないにしても ビジネスのうちの残り2割は やはり何かしらの理屈で 動いているわけです ここまでは理屈だけれど ここから先は理屈じゃない というように考えてみれば 理屈じゃないから 理屈が大切 という逆説が生まれます 「理屈じゃないんだよね」 という社長さんは意外ですが 結構理屈っぽい人が多く 論理的な話をされます 多くの中小企業の経営者は センスで仕事をされています いや、ビジネスなんて 理屈ではないんだよ と、のっけから感性に頼った ビジネスをしているだけでは 本当の意味での勘は鋭くなりません 成功する要素は「勘」が8割を 占めるとしても 2割の理屈を 突き詰めている人は 本当のところ 「何が理屈じゃない」のか 「勘」の意味合いを 深いレベルで理解しています 「ここから先は 理屈ではなく、気合だ」 という感じで 気合に頼らなければならない 境界線がはっきり見えています だからこそ ますます「気合」が入り 大切な「勘」を 研ぎ澄ませることができる 理屈じゃないから 理屈が大切なのです 理屈が重要な3つの理由 理屈が重要な理由が 3つあります 1つ目は 勘が重要だとしても限界があること そして勘の強みは 走りながら答えをだすこと 直感だけだと高速道路を走るように 自然と視野が狭くなります 2つ目は 優れた経営者が考える方針は とてもアーティスティックで 現実的にはサイエンスというより アートに近い部類です こういったものをチームで共有 したり、理解を促すためには 一度言語化しなければ 知見の利用範囲がきわめて狭くなります 3つ目は 理屈は、簡単に変わりません しかし 目の前の現象は日々変化します だからこそ 「変わらない何か」 としての理屈が大切になります プレジデントアカデミー 経営の12分野では 経営に必要な要素を 構築する様々な理論を 伝えていますが 効果的な要素を生み出すためには やはり勘というかセンスも必要です しかし、勘やセンスと 理屈の役割をしっかりと 理解して考えていくことで 面白い机上の空論を 打ち立てることが できるようになります この両方を鍛えて 魅力のある計画づくりに 挑戦したいものです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

物語のある計画
今日は自宅で クリスマパーティーです 今年もそろそろ 終わりに近づいてきましたね 皆さんはどんな1年だったでしょうか この1年、様々な変化がありました 当社は2月が新しい事業期なので 今はちょうど来年度の 経営計画書を作る時期です 自社の経営計画や事業計画を ずっと作り続けて感じることですが 計画には 優れた計画と そうではない計画 の2つがあります ビジネスの成功・失敗は 実際にやってみなければ わかりません 経営計画で成果のアタリハズレと 経営計画の優劣をかけ合わせると 4通りの組み合わせができます A.計画は優れていて、成果が出た B.計画は優れていてが、失敗だった C.計画は優れていていないが、成果が出た D.計画は優れていないし、失敗だった 成果で見れば AとCが成功で BとDが失敗です ビジネスという観点でみれば 成功よりも失敗の方が 間違いなく多いものです 野球でいえば 良い打者でも打率3割 全盛期のイチローのように 4割近い打者は奇跡の部類に属します ビジネスもそれに近いように感じます つまり、優れた計画をつくったとしても 結果から見れば7割くらいはBとなり Aに該当するのはせいぜい3割くらい どれほど計画が優れていたとしても 7割、8割の打率は実現できません ビジネスが直面している 競争と不確実性を考えれば 再現性の高い確率なんて かなり無理な話です では、計画が無意味かというと 決してそういうことはありません 計画が優れていたとしても 打率4割も期待できないのであれば こうした計画があってはじめて 打率4割が期待できるということで 良い計画がなければ成果がでるのは ずっとずっと難しくなります では、良い計画とはなんでしょうか 一番大きなポイントは そこに計画を大きく動かすための 物語があるかどうかです 具体的には 過去の失敗してきた計画の例を 記載したほうがわかりやすいかも しれません 各事業部に計画を具体化する スキルが十分に備わっていない 社員ばかりの時期がありました 全社の目標数字を各事業部に 割り当て具体化するところまでは できたとしても 実現性を裏付ける説得力のある 物語が不在でした 毎年経営計画をつくりますが 各リーダーは 3年先までの 売上やシェア、利益の数字は きれいに練り上げてくるものの 急にV字回復する物語や 一方的に自社のシェアが増える 物語がどのようにすすめられるのか 具体的に尋ねても答えられません 右肩上がりで売上や利益が増えている ステージでは済まされるもしれませんが 厳しいの環境下ではそうはいきません 現実的に考えようとすると 現状とのギャップを埋めるための 打ち手を現状の苦しい戦い方の 延長線上でしか考えることができず やはり現実感の乏しい数字だけが 先走った計画になっていました それでも形だけでも 市場環境やトレンド ターゲット・マーケットの分類 価格をどのようにするとか 協力会社の選定や 運営の組織体制をどうするとか 詳細に検討しているものもあります しかし、これでは項目ごとの アクションリストに過ぎません 結果的に、全体的にどのように動き 何が起きるのか その物語の流れが 繋がっていないものが多くあります 良い計画というのはこの物語が おもしろく、キレイに流れています それはもはや計画というよりは 妄想に近いものかもしれません ところがおもしろい 妄想は現実化することが多くあります そういった計画は 物語に引き込まれていきます 自分で作った物語に 自分自身が巻き込まれていく よい計画をあげてくれるリーダーは そういった人が多いものです ポジティブかどうか 本当はそんなことは あまり関係がありません ポジティブな人は ポジティブな物語を考え ネガティブな人は ネガティブな物語を考える その物語に 会社は巻き込まれていきます 運が悪いとか 才能がないとか 頭が悪いとか そんなことは関係なく 問題は成功する 物語をどうつくるか 物語とは妄想なので 勝手に考えていけばいいといえます 壮大な妄想を作り上げ 周りの人にそれを語る 語っているうちに 物語に巻き込まれる人が現れます 一人現れ、二人目が現れ 気がついた時には自分自身が その物語に取り込まれる まずは、当人が面白がれる 計画をつくれるかどうか 経営計画は そこが大切で つまらない 壮大なアクションリスト にならないようにしたいものです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー